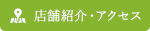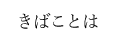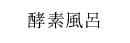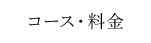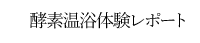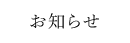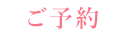カテゴリ
- もう、がんでは死なない (32)
- このクスリがボケを生む! (30)
- 口臭 (1)
- 47の心得 (77)
- アレルギー (4)
- 便 (13)
- 自律神経 (27)
- 運動 (24)
- メタボリックシンドローム (6)
- 体温 (42)
- 血液 (22)
- ストレス (41)
- 呼吸 (5)
- 酵素風呂きばこ案内 (51)
- ファスティング (6)
- 酵素風呂の記事 (10)
- 酵素栄養学 (79)
- 白湯 (8)
- 酵素とは? (11)
- 汗 (23)
- 酵素風呂 (53)
- 冷え (62)
- ダイエット (7)
- ゲルマニウム温浴 (7)
- プレ更年期1年生 (26)
- 医者が患者に教えない病気の真実 (57)
- 食品の裏側 (51)
月別 アーカイブ
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (5)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (5)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (5)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (7)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (7)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (6)
- 2019年12月 (7)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (7)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (7)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (7)
- 2019年2月 (6)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (6)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (5)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (8)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (11)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (13)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (11)
- 2016年10月 (9)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (11)
- 2016年7月 (19)
- 2016年6月 (21)
- 2016年5月 (14)
- 2016年4月 (6)
- 2016年3月 (1)
最近のエントリー
HOME > ブログ > アーカイブ > もう、がんでは死なない > 2ページ目
ブログ もう、がんでは死なない 2ページ目
ガン検診の考察
今回は「ガン検診の考察」というテーマです。
ガン検診が死亡率を減らせないことは、ガンが転移する時期を知れば自明です。
つまり、転移する能力があるガン(ガン細胞)は、初発病巣が発見可能な大きさ(1センチ)に育つずっと前に転移してしまっている。
そのため、検査でガンを発見しても臓器転移があるので、治せないわけです。
これが「本物のガン」です。
これに対し、転移能力がないガン細胞は数がいくら増えても転移できないため、放っておいても宿主が死ぬことがない。
「潜在ガン」のほとんどがこれで、見方を変えると「ガンもどき」です。
潜在ガンのような、放っておいても死なないガンを検査で見つけて手術して「治った」と言っても意味がないわけです。
自覚症状のない人に検診で発見される「ガン」に占める、ガンもどきと本物のガンの割合は部位によって異なります。
●前立腺ガン、乳ガン、子宮頚ガンは、ほぼ全てが「潜在ガン」であり「ガンもどき」です。
●胃ガン、大腸ガンはステージ1で見つかった場合には、ほとんどが「ガンもどき」です。
しかし、検診で進行ガンが見つかるケースもあり、その場合には「本物のガン」である可能性が高くなります。
●肺ガンはステージ1で見つかっても、「本物のガン」の可能性が2割程度あります。
ステージ3だと8割以上です。
●膵臓ガンは、ほぼ全てが「本物のガン」です。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年5月 9日 19:15
インフルエンザ脳症は薬害だった?
今回は「インフルエンザ脳症は薬害だった?」というテーマです。
解熱剤は死亡率をも高めます。
この点、動物実験では解熱剤を使うと無投薬に比べ、死亡率が上がることが示されています。
どの解熱剤でも、ウイルスの種類が違っても、解熱剤を使った動物の死亡率が上昇します。
また、人ではインフルエンザのような発熱性の感染症にアスピリン、ジクロフェナクなどを使うと「ライ症候群」が生じることがわかっています。
急性脳症が生じて死亡し、生き残っても麻痺や言語障害などが残るのです。
過去に「インフルエンザ脳症」とされてきた病態は、インフルエンザウイルスによるものではなく、「薬剤性脳症」つまり「薬害」と考えるのが妥当です。
脳症が生じる仕組みは「サイトカインストーム」(免疫物質の嵐)だと考えられます。
新型コロナでも、重症化原因に挙げられてきます。
サイトカインストームが起きる仕組みは、解熱剤で治るまでの期間が長期化する仕組みとほぼ同じです。
解熱剤で免疫細胞の活動が抑えられたあと、薬の影響が薄れて活動を再開した免疫細胞は、ウイルスが前より増えているのに驚いてしまう。
その結果、免疫細胞がウイルスと闘うために分泌する「サイトカイン」が大量に放出され、血流に乗って全身に回り、血管や肺などの臓器・組織を傷つけるわけです。
脳細胞がやられると「脳症」になります。
新型コロナでは高齢者や基礎疾患など「重症化因子」を持つ人で、サイトカインストームが生じやすく、死にやすいようです。
新型コロナで多数が亡くなっている欧米でも、解熱剤が当然のように使われていることが死亡率が高い一因なのでしょう。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年5月 2日 12:15
解熱剤で症状が長期化する?
今回は「解熱剤で症状が長期化する?」というテーマです。
「新型コロナウイルス」の初期症状は鼻水や咳、発熱や喉の痛み、筋肉痛などで、普通の風邪やインフルエンザと見分けることは困難です。
しかし、こんなご時世のため、風邪の症状があれば多くの方が「コロナでは?」と緊張・警戒をします。
ここで最も肝心なのは、熱があってもそれを下げる薬を飲まないことです。
具体的にはアスピリン、ロキソニン、イブプロフェン、アセトアミノフェンなどの「解熱剤」です。
薬局で売っているものも、医療機関で処方してされたものでも、説明文書に「解熱剤」とあったら、服用してはいけません。
解熱剤を飲むと、感染症状が長引き、重症化しやすいからです。
そもそも体温上昇は、ウイルスや細菌などの「病原体」が引き起こしているのではなく、身体の「調節システム」が指令して、筋肉を震えさせるなどして発熱させているのです。
熱が出たときに身体がブルブルと震えるのは、体温を上げるための作業なのです。
というのも、体温が高いほど病原体の活動が弱まり、逆にリンパ球など「免疫細胞」の働きが増強するからです。
それなのに、解熱剤で熱を下げると免疫細胞の働きが低下して、病原体が解熱剤を使う前より数を増やしてしまいます。
それで「いつまで経っても風邪がぬけない」となるわけです。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年4月25日 12:30
ガンもどき理論の強み
今回は「ガンもどき理論の強み」というテーマです。
ガンには2種類あります。
発見されたときに転移しているケースと、いつまでたっても転移できない「ケース」。
前者はガンと呼ぶのに相応しいので、「本物のガン」。
後者はいわばニセモノのガンなので、「ガンもどき」と呼びましょう。
ガンもどきは放っておいても、本物のガンに移行・変化しないのです。
では、両者の区別はできるのか?
ガンもどきと本物のガンは性質が大きく異なりますが、病理診断(顕微鏡検査)では、どちらも「ガン」と診断されます。
言い換えると、病理診断で「ガンもどきと断言できる」ケースは存在しないのです。
しかし、概念的には両者を区別することに実益があります。
まず、目の前の「ガン」がもし「ガンもどき」なら、転移が生じることはないので、放っておいても命取りにはなりません。
これに対して、もし「本物のガン」であれば、手術をしてもどこかに転移があるので治らない。
それどころか手術をすると、ガンが暴走して早死にする可能性があります。
このように「手術」との関係で、考え方を整理でき、方針決定に役立つのが「ガンもどき理論」の強みなのです。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年4月18日 12:37
ガンを放っておいても転移しないという根拠
今回は「ガンを放っておいても転移しないという根拠」というテーマです。
この根拠の基本は、「ガン細胞の増え方」です。
ガン細胞が誕生すると、2分裂を繰り返して2個→4個→8個と増えていき、ガン病巣が発見可能な1センチの大きさでは「10億個」ものガン細胞が詰まっています。
そこに至るまで5〜20年ほどかかりますが、「それほど長い間」「そんなに多数になるまで」転移できなかったこと自体が、ガン細胞に「転移する能力がない」証拠になるでしょう。
転移能力がなければ、その後いくら放っておいても転移できない道理です。
「いやいや、10億個になったあとも遺伝子が突然変異して、転移能力を身につける可能性がある」という反論はどうか?
これもやはり、「可能性」を論じるだけで、具体的なデータを示さない。
10億個になるまで転移できなかった、という事実は重いはずです。
いつ転移が生じるかに関しては、具体的な研究データもあります。
のちに東大外科教授になった草間悟氏が、米国留学時代に66人の乳ガン患者における転移病巣の大きくなり方を調べたデータです。
結果、ほぼ全員が早期発見可能な大きさのときに転移していました。
このように、ガンを放っておいても転移しないことは推論ではなく、観察事実に基づいています。
また、実験医学の分野でも証拠があがってきました。
例えば、乳ガンでは生まれて間もないガン病巣からガン細胞が離れ、転移してしまうことが確かめられています。
そうした実験結果を受け、世界で最も権威がある医学誌に「乳ガン転移のタイミング」という解説記事が載り、「ガン細胞は生まれた途端に転移し始める」という考えを支持しています。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年4月11日 18:37
ガンを放っておいたら転移するという根拠
今回は「ガンを放っておいたら転移するという根拠」というテーマです。
検査で発見できる大きさまで育った「ガン」を放っておいたら転移する、という話の根拠は次のとおりです。
①まず、ガン検診で発見されるような、自覚症状がない小さなガン、いわゆる「早期ガン」がある。
それらは転移しているケースが少ない。
②他方で、痛い苦しいなどの自覚症状で発見される大きなガン、いわゆる「進行ガン」が存在している。
そういうケースは転移していることが多い。
③だから、ガンが「早期ガン」から「進行ガン」に成長する間に転移するのだ、というのです。
とてもわかりやすい理屈ですが、この理屈には弱点があります。
それは実測データではなく、「推測」ないし「推論」なので、話の「前提」が間違っていると崩壊します。
●では、何が前提なのか?
それは「早期ガンが進行ガンに移行する」です。
もし、ガン検診で見つかるような早期ガンが進行ガンに移行しないのであれば、推論の前提は崩れます。
実際のところ、この「早期ガンを放っておくと進行ガンになる」という前提は未確認です。
なぜなら、これまで早期ガンは発見され次第、切除されてきたからです。
●では、進行ガンはどこから来たのか?
進行ガンも始まりは1個のガン細胞なので、それが増殖する途中、早期ガンと呼ぶのがふさわしい大きさの段階を経ています。
しかし、既に転移しているようなタチの悪いガンはどんどん増殖していくため、早期ガンとして見つかる機会がないか少なく、圧倒的多数が進行ガンとして発見されるでしょう。
これに対し、転移しないタチの良いガンは長い間小さいまま止まるので、いつ検査を受けても早期ガンとして発見されるわけです。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年4月 4日 15:26
ガンが自然に消えるアポトーシス現象
今回は「ガンが自然に消えるアポトーシス現象」というテーマです。
ガンが自然に消える仕組みに、「アポトーシス」という現象によるものがあります。
アポトーシスとは、「細胞の自殺」を意味し、それを引き起こすための仕組み、ないし装置が正常細胞に備わっています。
例えば、オタマジャクシがカエルになる前に尻尾が消えるのはアポトーシスによります。
また、人の胃や腸の「上皮細胞」は誕生してから、数日のうちに新しい細胞と総入れ替えされる。
このとき、古い上皮細胞はアポトーシスによって、自滅して消えていくのです。
但し、正常細胞が勝手にアポトーシスを始めると、身体の臓器や組織を形づくる細胞が焼失してしまいます。
それを防ぐため、多くの細胞は勝手にアポトーシスを起こさないように、それを抑制するための仕組みも備えています。
さて、ガン細胞は正常細胞から分かれたものなので、当然アポトーシスを引き起こすための仕組みを持っています。
ただ仕組みといっても、目で見えるようなものではなく、各細胞内の遺伝子やタンパク質の働き方を支持する「プログラム」のようなものです。
「アポトーシスを始めなさい」というスイッチが入れば、プログラムに従って細胞内の遺伝子やタンパク質が働きだすのです。
ガンが自然に消えるのも、各ガン細胞のアポトーシス・プログラムにスイッチが入ったためであるはずです。
但し、何がスイッチを入れるのか原因は不明です。
研究してもわからないのです。
そのため、「この食事で」「このサプリで」ガンが消えた、というような主張は科学的根拠がありません。
もっとも、抗ガン剤や放射線がガン細胞を殺すことがあるのは、それらがアポトーシス・プログラムのスイッチを入れるからではあるはずです。
しかし、このとき同時にガン細胞と同じプログラムを持つ正常細胞もアポトーシスが生じるため、死滅してしまうので、色々な副作用が生じるわけです。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年3月28日 11:26
抗ガン剤を中止したら、ガンが消滅?
今回は「抗ガン剤を中止したら、ガンが消滅?」というテーマです。
ガン細胞を殺すのが目的の抗ガン剤ですが、反対にガン細胞が消えるのを邪魔していることがあります。
抗ガン剤を止めると、転移ガンが消えるケースがあるのです。
例えば、肝臓ガンの肺転移と副腎転移のために抗ガン剤治療を受けていた男性が抗ガン剤を止めたら、全ての転移が消えたケースがあります。
他にも、膵臓がんから肝臓に転移したケースでは、抗ガン剤を(副作用が強いため患者の意思により)中止したら、全てのガン病巣が自然消滅したという報告もあります。
また、抗ガン剤の弟分のような「分子標的薬」についても、中止するとガンが消滅する現象が色々な分子標的薬で報告されています。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年3月21日 20:09
放射線によるバランス破綻に注意
今回は「放射線によるバランス破綻に注意」というテーマです。
あまり知られていないようですが、放射線治療も正常組織にダメージを与えるので、抵抗力の低下を招き、ガンが暴走することがあります。
つまり、放射線が照射された部位とその周辺にガンが再発してくることがあるのです。
例)小さな肺ガンを放射線で治療するケース
このときに用いられるのが、「定位放射線治療」です。
小さな病巣を狙って、四方八方から放射線を集中的に照射するので、「ピンポイント照射」とも呼ばれています。
しかし、放射線はそれが通過する周辺組織にもダメージを与えます。
このダメージを受けた肺組織は、ガン細胞に対する抵抗力が弱っているので、血液中に存在しているガン細胞が定着しやすく、増殖して「再発病巣」になります。
照射された部位とその周辺にポツポツとガン病巣が生じるのです。
なお、ピンポイント照射の全てに生じるのではなく、どこかの臓器に転移している「タチの悪いガン」の場合に、この形の再発が起こりうるわけです。
そして、血液中にガン細胞が存在するがゆえに、放射線ではなく手術を選んでも、メスが入った「局所」や遠くの「臓器」に再発してくるはずです。
色々な臓器や部位で、放射線によるガンの暴走現象が生じているはずです。
しかし、元々「ガン」が存在していた部位やその周辺でガン細胞が増殖するので、「ガンの局所再発」とみなされ、臨床現場で問題になることは多くありません。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年3月14日 12:03
ガンを暴走させる増殖因子
今回は「ガンを暴走させる増殖因子」というテーマです。
ガンが暴走する理由の1つとして、手術後に分泌される「増殖因子」というものがあります。
ケガをした場合を考えてみましょう。
●擦り傷など「ケガ」をすると、傷口に白血球などが集まって種々の「増殖因子」を分泌します。
それが正常細胞を活性に分裂させ、組織は修復されるわけです。
●ガンの手術は「大ケガ」なので、分泌される「増殖因子」が擦り傷などよりも桁外れに多くなる。
●ガン細胞は、その仕組みと働きが正常細胞とほぼ同じなので、増殖因子に反応して、急激に増殖・増大することになります。
他方で、転移ガンが暴走するようなケースでは、手術前から臓器に転移ガン細胞が隠れています。
その場合に手術すると、メスが入った部位で大量の「増殖因子」が分泌され、それが血流に乗って全身を巡り、色々な臓器に隠れている転移ガン病巣を刺激し、暴走を始めさせるわけです。
整理すると、
①手術によって正常組織の「抵抗力」が破綻し、そこにガン細胞が入り込む。
②手術によって生じる「大ケガ」に対する人体の反応である「増殖因子の分泌」が手術部位や遠くの臓器でガンを急速に増大させるわけです。
結局、ガンと正常組織の「抵抗力」との間に成立していた「バランス」が手術によって崩れ、ガンの暴走が生じるわけです。
<参考文献>
もう、がんでは死なない ~二人に一人ががんになる時代の最高の治療法~
(マガジンハウス・2020)
著者:近藤誠
(きばこ酵素風呂) 2022年3月 7日 18:57